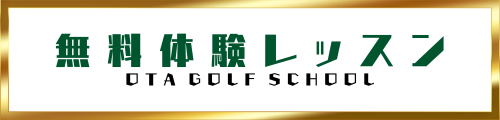インパクトの効率を上げるために入射角を最適化するのがシャローイングOTAゴルフスクール名古屋にも、シャローイングを採り入れているアマチュアが指導を受けに来ることがあります。 中には、シャローイングがうまくいかずに悩んでいる人も当然います。そんな人ほどセカンドショットで「ダウンスイングの形」や「ハンドファーストのインパクト」ばかりを意識している傾向が見られるそうですと。そこでインストラクターに「シャローイング」の意味と採用するべき人について聞きました。 そもそも「シャローイング」とは、インパクトの入射角が鋭角すぎるスイング軌道を、浅い入射角へと最適化するのを目的とするスイング理論。 適正な入射角はヘッドスピードによって変わりますし、多少の個人差はあって当然です。しかしスピン量が多すぎて飛距離をロスするほどでは、改善すべきです。 つまり「シャローイング」の動画で特徴として見られる「ダウンスイングでシャフトを倒すかどうか」という形にこだわるのではなく、インパクトの入射角がヘッドスピードに合った最適な角度になっているかに着目しなければ意味がありません。 また、目視できない非常に速いヘッドスピードの入射角を修正するのは、アドレスやバックスイングよりも改善するのが、むずかしいことも理解しておいてください。 ダフらずボールが上がる人じゃないとシャローイングは意味がない「シャローイング」はインパクトの入射角を最適化するのが目的です。その前提として、スイングがある程度安定していることが条件となります。 いわば上級テクニックなのですが、ビギナーなど誰でもナイスショットできるようになると思い込んでしまうのは、とても危険です。 特に、緊張している本番だけでなく練習時でもダフリが出ていたり、スピン量が足りていないゴルファーが取り入れてしまうのは逆効果といえます。 ハンドファーストにするのも同様ですが、ロフトの立った飛び系アイアンを使っていて低い弾道のショットしか出ていない場合も、「シャローイング」はオススメしません。 理由は「シャローイング」のヘッド軌道は鈍角(シャロー)になるからです。すると、鋭角な軌道に修正すべきダフリ気味の人では真逆になってしまいます。鈍角なインパクトはスピン量を減らすので、低スピンや低弾道の人にとっては意味がありません。 今いったような悩みの人は、「シャローイング」を検討する以前に「ボールの先のターフをしっかり取る」というダウンブローインパクトを習得する方が先決です。 少なくともラウンド時のセカンドショットでダフリがまったく出ない自信をつけてから、もっと効率のいいショットを打つために「シャローイング」に取り組むべきか考えるようにしましょう。 「上から下」のヘッド軌道を覚えてからシャローイングに取り組むべき当たり前ですが、アイアンのセカンドショットではボールよりも目標寄り(先)にヘッド軌道の最下点があるべきです。つまり、どれだけ「シャローイング」しても、インパクト時のヘッドは「上から下」に動いていなければボールにきちんとコンタクトできません。 地面にあるボールを打つので、ボールより手前で最下点を迎えてはダフリになります。その重要なインパクトの軌道を忘れ、ネット動画の大げさな「シャローイング」の体やクラブの動きを真に受けてしまっているアマチュアも数多く見かけます。 繰り返しになりますが、「シャローイング」の目的はヘッド軌道の最適化であり、飛距離アップや方向性の安定などは、最適化された結果なのです。 「シャローイング」の言葉の響きやスイングの形は、飛びそうでかっこよく見えてしまうかもしれません。しかしコースでナイスショットを打つために必要なことには、もっと現実的で実践可能なものがたくさんあります。流行りのスイングに興味を持ってトライすること自体は感心しますが、試してみてうまくいかなかったら「基本に戻る」ことも忘れずに取り組んでみてください。
0 コメント
「右向いてるよ!」の原因は練習打席にあった!? 北は北海道、南は沖縄まで、私は全国のゴルフ練習場を訪れてゴルファーのみなさんにレッスンをさせていただいてきました。そこで気付かされたのは、普段の練習やラウンド環境がスイングやプレースタイルに影響を与える傾向が強いということでした。 例えば、普段から天井が低い打席で練習しているアマチュアは、トップもフィニッシュも低いスイングになりがち。この傾向は、個人差こそあれ、打席の端から端までを見て感じたことです。 また、打席の天井の高さは十分でも隣の打席が近くて狭い練習場では、スイングはタテ振りになったりアウトサイドイン軌道になっている傾向が見られました。高さも幅も十分に広い打席で練習しているアマチュアは「まさか」と思うでしょう。でも、全国にはスイングをするのにギリギリの設計の練習場もあり、打席スペースの強いバイアスがスイングに大きな影響を与えているのも事実です。 最近は、打席スペースがとても狭いインドアゴルフレンジもあります。練習代が安いかも知れませんが、意識の有無に関係なく練習を行う打席の空間によってスイングが決まってしまう危険性を知っておいて欲しいです。 特にアマチュアの多くが悩むアウトサイドイン軌道は、横幅が狭い打席ではレッスンを受けても改善するのがむずかしいというのが現実です。 また練習場では、奥のネットの正面と打席が向いている方向との関係にも注意が必要です。打席の向きがズレていると、ターゲットに対するアドレス向きが左右にズレて体にインプットされてしまうことがあります。コースで「右向いてるよ」と指摘される人は、普段練習している打席がネットの正面に対して右向きになっている可能性があります。 完全に四角い打ちっぱなしの練習場は基本的にありません。自分が真っすぐ構えられる打席で練習するか、打席が左右どちらに向いている場合はそれを認識したうえで正しくアドレスできるように練習を工夫してみてください。 一人のティーチングプロに長く習うほど「好み」や「クセ」が移りやすくなる レッスンを受けているアマチュアは、一人のティ―チングプロに長く習うほど「好み」や「クセ」がプロと似てしまう傾向があります。 もちろん一人のプロに長く習うことで、情報に振り回されず「迷わない」というメリットもあります。しかし一方で、それが理論的に間違っていなくても、偏ったスイングに対する考え方やプレースタイルに陥ってしまうデメリットもあります。 そうならないため、OTAゴルフスクールでは複数のプロの目で生徒さんをチェックしてカルテを共有。標準化されたスイングを身につけてもらえるように、個々のゴルファーにやるべきことを指南しています。 一人のプロに長く習っていて上達しているなら、いい方向に進んでいるといえます。ですが、上達に停滞を感じているのならば、セカンドオピニオンを考える時期だと思います。 特に、スコアの推移やスイング動画、弾道測定結果といった可視化できる指標や目標がなく、「先生がそういったから」という理由だけで練習に取り組んでいる人は一度立ち止まってみましょう。先ほどいったように、プロの「好み」や「クセ」ばかりが似てしまうことになりかねません。 よく行くコースの距離や広さによってプレースタイルは影響を受ける 練習環境だけでなく、ホームコースなどよく行くゴルフ場の特徴によっても、プレースタイルは影響を受ける場合があります。 昔からゴルファーの間で「風が強いコース育ち」や「狭いコース育ち」といった言葉が交わされてきたのは、その証拠です。 距離が短かくて左右の狭いコースでは方向重視になり、距離が長くてフェアウェイが広いコースでは飛ばし重視のプレースタイルになるものです。例えば、いつも風が強くて左右が狭い河川敷コースの主たちは、トップもフィニッシュも低いスイングでラン主体のライナー性のショットを打つ人がほとんど。 一方、距離が長くて池やコーナーを越えるキャリー重視のチャンピオンコースでプレーしていると、大きなスイングと大胆なコースマネジメントが自然と身につくものです。 またアマチュアの場合、仲間内のうまいゴルファーのプレースタイルに影響を受ける傾向があります。左右が狭くペナルティーエリアが多いコースを攻略するうまい人をマネしようとすれば、自然とライン出しショットや刻むプレースタイルを理想と考えるようになります。 一方、広いコースを飛距離で圧倒するうまい人と普段からプレーすれば、飛距離や大きなスイングアークを目指したくなるものです。 どんなゴルファーも、得意なコースや相性のいいコースがあります。普段の練習環境やホームコースのラウンドに課題や壁を感じたら、いつもと違う特徴のコースや仲間とプレーしてみることをオススメします。違うプレースタイルを発見して、目からウロコが落ちるかも知れません。
スロープレーは腕前を問わず意識次第で防げる いわゆる“二郎系のラーメン屋”などでは、数人分の麺をまとめて茹でるロット制を採用していますが、誰かがダラダラと時間をかけて食べていると“ロット乱し”となり、店や後ろに並んでいる人たちに迷惑をかけてしまいます。 ゴルフの場合は誰か1人の“スロープレー”が、同伴者や後続組だけでなくコース全体の進行を遅らせる可能性も。ビジネスでいえば、全体のボトルネックになってしまうのです。最悪の場合は後続組とのトラブルに発展することも考えられます。 では、スロープレーにあたる行為や、同伴者や後続組が「遅い」と感じてしまう場面には、どのようなものがあるのでしょうか。 「スコアを多く叩いてしまう人ほど、プレー時間がかかるのは致し方ないことですが、意識づけと準備次第で“スロープレーヤー”になること自体は避けることができます。」 「構える前には諸々の『決断』を終えておくべき」 「そして、構えた後は足踏みやワッグルなどでリズムを取りつつ、スムーズに始動するのがオススメ。体が完全に停止した状態から始動するのは難しく、スイングがギクシャクしやすいため、ミスショットの確率が逆に高まってしまいます」 「練習場ではパンパンとリズムよく打っているのに、コースに出ると慎重になりすぎて固まってしまう人もよく見ますが、コースでこそ練習場のようにリズムよく打ってほしいところです」 後続組から見ても“悪目立ち”する行為とは? では、直接的なプレー以外では、どのような行為がスロープレーとみなされやすいのでしょうか。 「セルフプレー時の基本にはなりますが、ショット地点には使う可能性があるクラブを必ず数本持っていくことが大切です。特にグリーン周りでは、アプローチ用のクラブとパターをセットにして忘れずに持っていくようにしましょう」 「クラブ選択はライや風、どんなショットを打ちたいかで変わってきますが、1本ではそもそも選択肢がない状態と言えます。そして、ショット地点からカートまでクラブを取りに戻る行為は時間も体力もムダに消耗するうえ、後続組から見ても“悪目立ち”するので避けたいところです」 「そのほかにも、『何が何でもカートに乗る』『万が一にも届かない距離なのにグリーンが空くまで待っている』といった行為もスロープレーにつながるでしょう。私の場合、ビギナー向けのショートコースレッスンでは、スイングやマネジメントだけでなく、スロープレーにならないような“回り方のコツ”も伝えるようにしています」 筆者自身もつい先日、ゴルフ場で以下のような行為を目にして「遅いな……」と感じてしまったことがありました。 右の林に打ち込んだティーショットを同伴プレーヤー“全員”で探しに行き、なかなか戻ってこずカートだけがポツンと停まっていた場面です。 同サイドに打ったプレーヤーがボール探しを手伝うのは当然として、逆サイドのプレーヤーは、まず自身のボールを打って組全体のプレーを進行しつつ、その後にボール探しの役割を別のプレーヤーと交代してほしいところでした。 同伴者にはもちろんのこと、後続組や他のプレーヤーにも配慮してプレーを進めることがゴルフの鉄則。スロープレーを撲滅し、一人一人がプレーファストを心掛けて進行することが、より気持ちよくラウンドを楽しめる第一歩となるはずです。
|
OTAゴルフスクールは、初心者の方でも安心して通える 少人数制のゴルフスクールです。 基礎を大切にし、長くゴルフを楽しめる環境づくりを行っています。
八事校
名古屋市昭和区八事本町103-1
名古屋市昭和区八事本町103-1
東山公園校
名古屋市天白区天白町八事裏山170
名古屋市天白区天白町八事裏山170
体験レッスン申込フォーム
|
入会のお手続き
|
予約方法・利用ルール
|
退会のお手続き
ゴルフインストラクター募集(名古屋)
|
サイトマップ
|
会社情報
|
関連リンク
|
プライバシーポリシー
|
特定商取引法に基づく表記
|
お問い合わせ
©️ Ota Golf School All rights reserved.