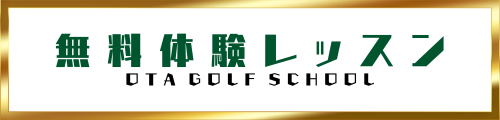インパクトの効率を上げるために入射角を最適化するのがシャローイングOTAゴルフスクール名古屋にも、シャローイングを採り入れているアマチュアが指導を受けに来ることがあります。 中には、シャローイングがうまくいかずに悩んでいる人も当然います。そんな人ほどセカンドショットで「ダウンスイングの形」や「ハンドファーストのインパクト」ばかりを意識している傾向が見られるそうですと。そこでインストラクターに「シャローイング」の意味と採用するべき人について聞きました。 そもそも「シャローイング」とは、インパクトの入射角が鋭角すぎるスイング軌道を、浅い入射角へと最適化するのを目的とするスイング理論。 適正な入射角はヘッドスピードによって変わりますし、多少の個人差はあって当然です。しかしスピン量が多すぎて飛距離をロスするほどでは、改善すべきです。 つまり「シャローイング」の動画で特徴として見られる「ダウンスイングでシャフトを倒すかどうか」という形にこだわるのではなく、インパクトの入射角がヘッドスピードに合った最適な角度になっているかに着目しなければ意味がありません。 また、目視できない非常に速いヘッドスピードの入射角を修正するのは、アドレスやバックスイングよりも改善するのが、むずかしいことも理解しておいてください。 ダフらずボールが上がる人じゃないとシャローイングは意味がない「シャローイング」はインパクトの入射角を最適化するのが目的です。その前提として、スイングがある程度安定していることが条件となります。 いわば上級テクニックなのですが、ビギナーなど誰でもナイスショットできるようになると思い込んでしまうのは、とても危険です。 特に、緊張している本番だけでなく練習時でもダフリが出ていたり、スピン量が足りていないゴルファーが取り入れてしまうのは逆効果といえます。 ハンドファーストにするのも同様ですが、ロフトの立った飛び系アイアンを使っていて低い弾道のショットしか出ていない場合も、「シャローイング」はオススメしません。 理由は「シャローイング」のヘッド軌道は鈍角(シャロー)になるからです。すると、鋭角な軌道に修正すべきダフリ気味の人では真逆になってしまいます。鈍角なインパクトはスピン量を減らすので、低スピンや低弾道の人にとっては意味がありません。 今いったような悩みの人は、「シャローイング」を検討する以前に「ボールの先のターフをしっかり取る」というダウンブローインパクトを習得する方が先決です。 少なくともラウンド時のセカンドショットでダフリがまったく出ない自信をつけてから、もっと効率のいいショットを打つために「シャローイング」に取り組むべきか考えるようにしましょう。 「上から下」のヘッド軌道を覚えてからシャローイングに取り組むべき当たり前ですが、アイアンのセカンドショットではボールよりも目標寄り(先)にヘッド軌道の最下点があるべきです。つまり、どれだけ「シャローイング」しても、インパクト時のヘッドは「上から下」に動いていなければボールにきちんとコンタクトできません。 地面にあるボールを打つので、ボールより手前で最下点を迎えてはダフリになります。その重要なインパクトの軌道を忘れ、ネット動画の大げさな「シャローイング」の体やクラブの動きを真に受けてしまっているアマチュアも数多く見かけます。 繰り返しになりますが、「シャローイング」の目的はヘッド軌道の最適化であり、飛距離アップや方向性の安定などは、最適化された結果なのです。 「シャローイング」の言葉の響きやスイングの形は、飛びそうでかっこよく見えてしまうかもしれません。しかしコースでナイスショットを打つために必要なことには、もっと現実的で実践可能なものがたくさんあります。流行りのスイングに興味を持ってトライすること自体は感心しますが、試してみてうまくいかなかったら「基本に戻る」ことも忘れずに取り組んでみてください。
0 コメント
あなたのコメントは承認後に投稿されます。
返信を残す |
OTAゴルフスクールは、初心者の方でも安心して通える 少人数制のゴルフスクールです。 基礎を大切にし、長くゴルフを楽しめる環境づくりを行っています。
八事校
名古屋市昭和区八事本町103-1
名古屋市昭和区八事本町103-1
東山公園校
名古屋市天白区天白町八事裏山170
名古屋市天白区天白町八事裏山170
体験レッスン申込フォーム
|
入会のお手続き
|
予約方法・利用ルール
|
退会のお手続き
ゴルフインストラクター募集(名古屋)
|
サイトマップ
|
会社情報
|
関連リンク
|
プライバシーポリシー
|
特定商取引法に基づく表記
|
お問い合わせ
©️ Ota Golf School All rights reserved.